33歳の時、客室乗務員(キャビンクルー)になるチャンスを得た。 しかし、同期で一番落ちこぼれな私は、かなり追い込まれていた。
前回の話し。
ホームシックで日本が恋しいが、落ちこぼれて、強制送還にて日本帰国というシナリオは自分の頭にはなかった。
これはいかんとそこからメソメソ考えるのはやめて、必死に勉強し始めてたら、だんだん集中力が高まってきた。
訓練では、実践訓練もある。
まずは、Door operating proceduresと呼ばれる飛行機のドアの開け閉め。

また、機内は禁煙だが、
乗客の喫煙違反行為の対応、
給油時の注意事項、
車いすやストレッチャーなどの特別な援助を必要な乗客の対応、
コックピットのやり取りの注意点などなどたくさんだ。
また、機内には、多くの安全設備がたくさんあることを知った。
乗客の目に触れないところに消火活動に必要なものや、サバイバルグッズ、電灯やらがあった。
私の会社は、エアバスの機材を使用し、国際線は、「330」という1種類だった。
最初はそれだけ覚えればよかった。
途中から、国内線も飛んだりで他の機種のトレーニングも始まった。
似ているのだが、やはり同じではないので、新たな訓練が必要になる。
覚えるのも大変だ。

私の友人は世界中を飛ぶエアランで働いていたのだが、ボーイング社というエアバスの対抗航空会社の機種でも飛んでいたので、全部で10機ほど覚えたらしい。すごい。。
そして、急病人発生時のファーストエイド。
病気の兆候や、症状などの知識を学ぶ。
鼻血、飛行機酔い、歯痛という軽症のものから、心臓発作や脳梗塞などの命に危険にさらされることに関しても学ぶ。
ドクターの資格を持つ講師がやってきて、CRP(心臓マッサージ)の指導を受けた時は、説得力のある、彼らの体験談を聞けた。

また、AED(心臓救命装置)での訓練。
心臓マッサージをしてから、電気ショックを入れる。
幸い、5年のクルー人生で使用することはなかった。

また機内では、さまざまなことが起こりうるということを学んだ。
低酸素症、失神、貧血、やけどなど。
酸素ボンベを使っての酸素吸入は、実際にかなりの回数をやった。

初めての時は、かなり緊張したが、周りのクルーが手慣れていたので助かった。
2回目からは、大丈夫になった。
何事も経験しないと始まらないと感じた。
また、飛行機に持ち込めない危険物や、ハイジャックされた時の対応法は、2001年9月11日の米国同時多発テロ以降、世界的に厳しい規則になったそうだ。
私は、この911に強い思いがある。なので気が引き締まった。(過去投稿👇)
それに不随して、機内全体の安全を脅かさないために、セキュリティ関係のトレーニングもあった。
例えば、手に負えない乗客、爆弾予告などの素早い対処の仕方や早く気付くための手段などだ。
機内での安全阻害行為を行う乗客への対応では、警察官が来て、自己防衛法を教えてくれた。

Stay Back!!後ろに下がれ!と大声を出せと指導を受けた。
ハイヒールを仕事中に女性は履いているので、
「すねを上からえぐるように蹴り倒せ!」
と力強い声が飛んだ。
うっす、うっす、うっす!
マニュアルを見ながらできる唯一の試験があった。
火薬や火気などの機内持ち込みなど、安全飛行を脅かす可能性のあるDangerous goodsの規則に関するテストだ。
とはいっても、全て英語。
見慣れない単語ばかりだったので、ちっとも楽ではなかった。
そんなわけで、必死にやっていたら、くよくよしている時間もなくなって、元気が出てきた。
そして、一番大変な訓練が待ち受けていた。
しかし、この続きは、また次回の搭乗の際に、お話しさせていただきます。
本日もご搭乗いただき誠にありがとうございました。
次のお話し↓
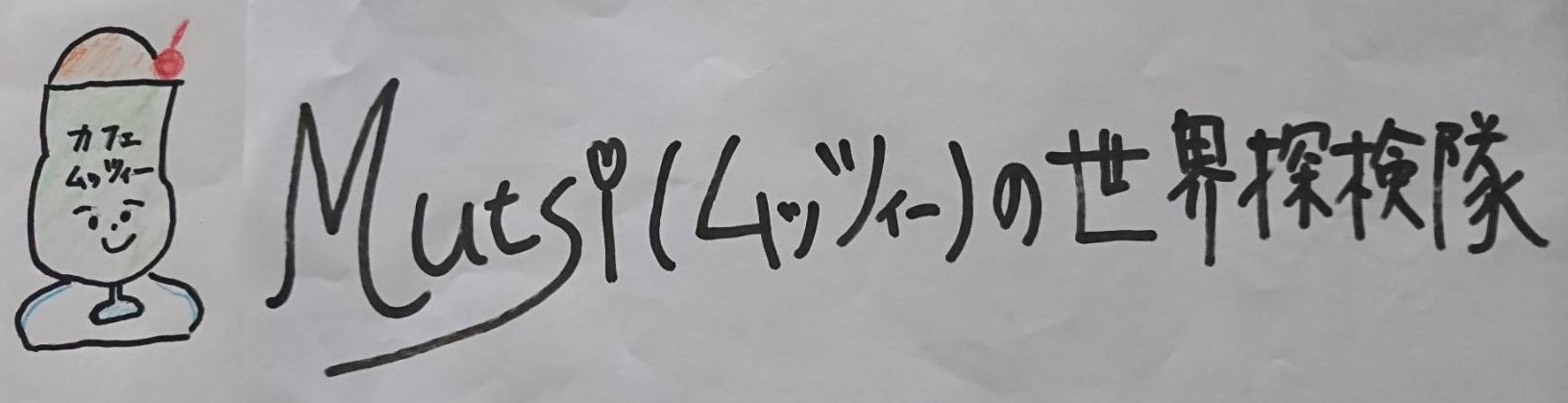




コメント
[…] 【海外就職】スチュワーデス物語 訓練生編2 […]