こんにちは。突然だが、アメリカ人の団体ツアー手配の仕事を1年ほどしたことがある。
ツアー中にガイドさんが、グループ全体を率いている時の席で話してはならない3つの項目を教わった。
「政治」「宗教」「収入」だ。
20日間ほど、平均15名ほどの団体を引き連れて、案内をする。
長い道中、グループによっては、いざこざがある。
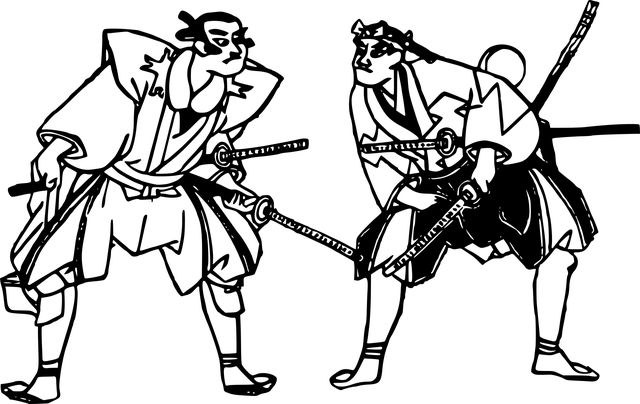
お客さんは、退職者を対象にしていた。
先生が多く、弁護士、医者などもいて、いわゆる「そういう地位」の人達のツアーだ。
主張の強いアメリカ人。
政治に関しては、意見も真っ二つに分かれる。
私がその仕事をしていた当時は、あのトランプ政権時代だ。
支持派と反対派が一緒なグループなのでややこしい構造になる。
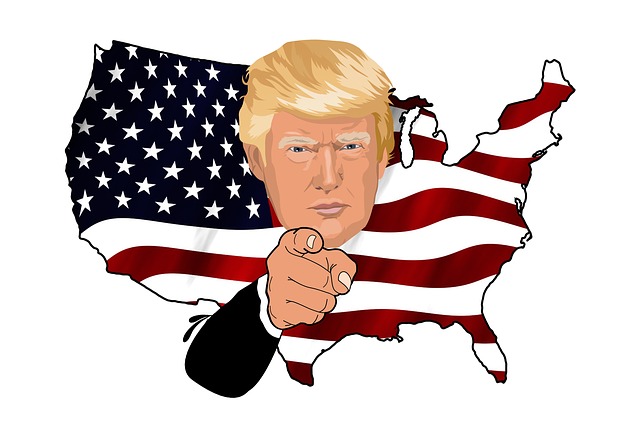
ガイドさんも色々大変だっと思う。
そんなわけで、私もこういう場であまり政治的な発言はしたくないのだが、選挙が近いとのことで、今日は、ちょっとご紹介したい話しがある。
私は、2005年にニュージーランド(NZ)にいたのだが、その年に選挙がこの国でもあり、家族や友人にNZの選挙の様子を伝えた文章を今も持っている。
ちょっと読んでみたら、自分でいうのも何だが、とても面白かったので、今日はこちらを紹介したい。なかなかの長文なので2回シリーズでお届けする。
なお、その当時、私なりに報道記者のように調べて、体験したものだが、恐らく間違っている情報もあると思う。
あくまでもあの頃の私の周りの小さな世界での記者もどきが、語っているものと思って、温かい目でみていただけるとありがたい。
それでは、はじまるよ。MutsiのNZ選挙リポート!

2005年9月18日
皆様こんにちは。
昨日の9月17日、ここ、NZで3年ぶりの総選挙があった。
こちらの国会はイギリス式。
つまり、日本と同じ体制になるが、上院のみで下院はない。
総選挙は、3年ごと。
この国は、世界で初めて、女性参政権を取った国だ。
10ドル札になっているケイト シェパードが1893年に権利を獲得した。
これは、イギリスよりも25年早く、歴史が浅い割には、このような斬新なアイデアを取り入れ、女性が非常に活躍している国である。
現在の首相はヘレンクラークという女性で野太い声を出す、たくましい女性だ。

数か月前、日本を訪問した際、小泉首相とも会談していた。
NZの選挙権は、18歳以上の市民権、または永住権保持者が持っている。
初めて、選挙をする人は、登録を役所にしに行く必要がある。
選挙は、日本と同様、強制義務ではないが、国民の80%が登録しているそうだ。
ちなみにお隣のオーストラリアは、選挙に行かないと罰金だ。20ドルほどになる。
バーで生ビール3杯ほどだ。
そんなわけで、選挙の話題は、9・17が近づくに連れて増してきた。
選挙運動は、日本のような選挙カーで名前を朝からマイクで叫んだり、街頭演説はない。
看板は、掲げられるが、日本ほど多くはなく、選挙の1週間前くらいから、朝の通勤の際に、各政党の看板を持った人が、私達に手を振るくらいだ。
しかし、テレビは、討論番組が増え、各政党のリーダーが勢ぞろいすることもしばしばある。
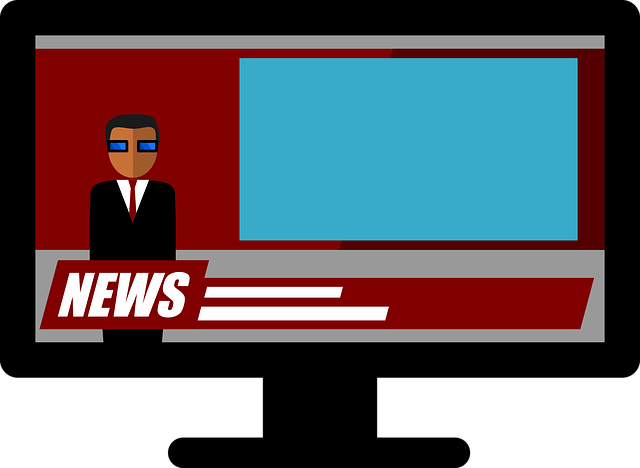
政党は、9つほど。
アメリカのように赤と青でわかりやすく政党が分かれる。
現在の与党が赤の労働党。
ヘレンクラーク首相は、2期6年と続き人気。
何よりもリーダーシップがある。
温情的、知的、有能といい言葉で褒められている。
対抗馬の最大野党が保守派の青色、国民党。
この国民党が今回、大々的な減税対策を打ちだし、国民の関心度が一気に増した。
特に子供を持つ家庭には、嬉しい減税対策案だ。

その結果、支持政党真っ二つにわかれ、いよいよ政権交代か!と選挙運動が熱くなっている。
この国も日本と同様、医療、教育、税金、経済、治安など様々な問題を抱えている
私のKIWI(ニュージーランド人)の友人も
「医療対策は、労働党、税金対策は、国民党支持だから、どっちに投票しようかなー」
と言った具合に、多くの人が決めかねていた。
支持率もテレビ、新聞で発表される数字がそれぞれ違い、蓋を開けるまでわからなくなってきた。
前日の大手新聞ヘラルドに出てきたデーターを分析すると、

労働党の支持者は、ヘレンクラーク支持者の女性からの圧倒的人気。
また、低所得者、若者の支持も得ている。
移民、難民受け入れに開放的。
対する、青の国民党の党首は、ドン ブラッシュという男性。
支持者の多くは、40代から60代の男性、富裕層。
移民受け入れ、慎重派だ。
私はこの国の選挙権はないが、個人的には赤の労働党派だ。
そんなわけで、いよいよ選挙日がくる。
ーー
というのが、選挙前日までのレポート。
本日はここまでにしたいと思う。
選挙当日の様子は、こちらです。↓
というわけで、またねーー
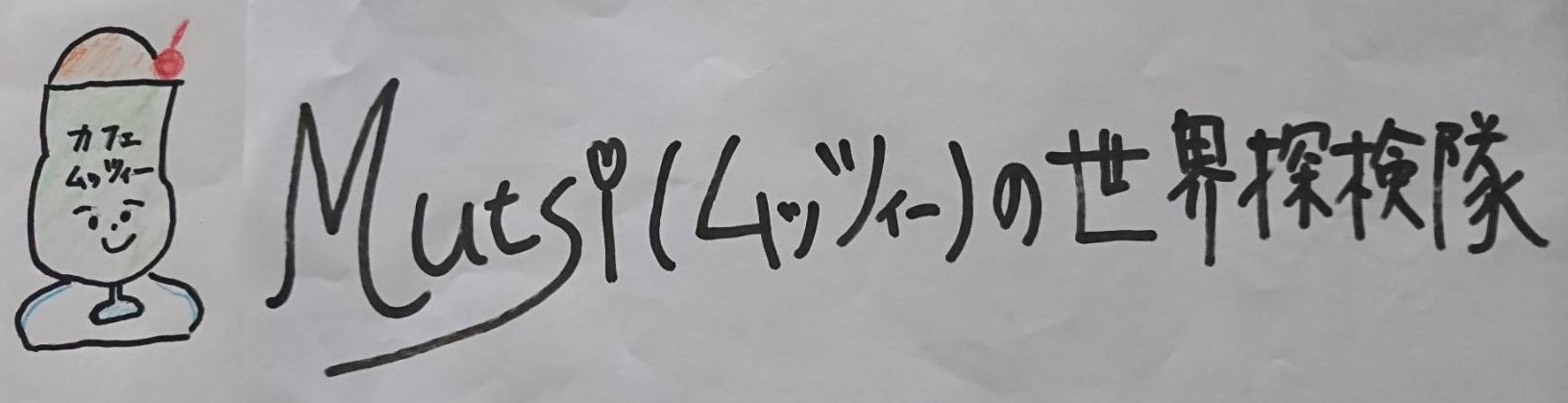



コメント